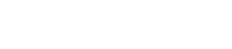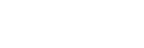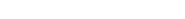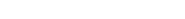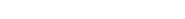京都 増原ひろこ
HIROKO MASUHARA
LGBTコンサルタントとして有名な増原ひろこは、自身もレズビアンであることを公表している。自分自身のリアルな経験を語る著作や、どんな人でも働きやすい職場づくりに関する数々の著作を発表し、セクシュアル・マイノリティだけでなく、様々な人たちが生きやすい社会を実現しようと活動してきた。過去にはNTTドコモのCMに出演したことも。昨年春には、経済評論家の勝間和代さんとの交際も話題になった。
そんな彼女は昨年末から、この夏にむけて京都で政治活動を開始した。これまでの企業のダイバーシティ経営を推進するコンサルティングや、講演活動などを通じて「社会が動いている」と手ごたえは感じていた。しかし政治がなかなか実情には追いついては来ない状況に危機感をおぼえての決断だ。政党の候補者を男女同数にすることを目指す“日本版パリテ法”が成立したことも、背中を押したという。
「今の日本社会で息苦しいと感じているのは、きっとマイノリティだけじゃないはず」。最近では、LGBTには「生産性がない」、「LGBTばかりになったら国が滅びる」…そうした政治家の発言が相次いでいる。まったく未経験の政治の世界に飛び込む彼女に、これまでのライフ・ストーリーと、目指す社会のビジョンについて聞いた。
コンサルタントとして、そしてLGBT当事者として
──簡単に自己紹介をお願いします。
増原ひろこです。トロワ・クルールという会社の代表で、企業のダイバーシティ経営、つまり「誰もが働きやすい環境づくり」という取り組みのコンサルティングや研修、講演活動をしてきました。

──増原さん自身、2011年にレズビアンであることを公表されて、社会的な発信を続けてきました。
そうですね。わたし自身、自分のセクシュアリティについてずっと誰にも言えずに苦しんで、大学卒業の頃にやっとそのことを周囲に伝えることができました。その経験は、これまでの活動でも、これからの活動でも、原点になっていると思います。
昨年12月から京都で政治活動を始めました。わたし、大学院時代に京都と姉妹都市であるパリに留学していたんですが、京都には鴨川、パリにはセーヌ川があり、何より自由な雰囲気が共通しています。大変なこともあるけれど、毎日わくわくしながら頑張っています。

いわゆる「体育会系」で、外からみれば「優等生」。でも…
──子ども時代の話を聞かせてください。
わたしには兄と弟がいて、3人きょうだいの真ん中。小さい頃からすっごい活発でした。「男の子の遊びでしょ」と言われるほうに興味を持つタイプで、兄や弟と一緒に、泥だらけで野球をやったりしてましたね。いわゆる「おてんば」ですね。
中学と高校では陸上部で100メートルと200メートル競技に打ち込んで、大学では週6でバスケットボール部…つまり根っからの「体育会系」です。意外に思われることもあるんですが。

──では学校でもけっこう優等生でしたか?
だと思います、たぶん。外から見たら、スポーツもできてわりと成績も良い、私生活でも特に問題もないように見える「優等生」だったんじゃないかな。でも、誰にも言えない秘密を抱えて、ずっと不安と孤独がありました。

好きな子からの「気持ち悪い」という言葉が心に刺さった
──著作などでは、小学生の頃に「なにか周りと違うな」という違和感を持ち始めた、と言っていました。
そうですね。小学生の頃から、「好きだな」って思う相手が女の子だったんです。周囲の女の子たちが、好きな男の子のことを話している時に、「自分は周りと違うのかな?」って幼心に思い始めました。
小学校5年生の時、好きだった女の子がいたんです。ある日、わたしがその子のことを無意識に目で追っていたら、「こっち見ないで。気持ち悪い」と何気なく言われて。その言葉が心にグサッと刺さりました。
──そうしたことは周囲に相談できましたか?
いえ。学校の中でも、男の子たちの中で、いわゆる「ホモネタ」と呼ばれるジョークが飛び交うことが頻繁にあったし、「絶対にバレてはいけない」「いじめられるかもしれない」という恐怖がどんどん強くなっていきました。誰にも相談できなかった。

12年続いた「暗闇のトンネル」
──誰にも相談できない時期というのは、長く続きましたか?
小学校高学年から大学を卒業するまで12年間。長い暗闇の時期ですね。トンネルの中にいる感じ。わたしが高校生の頃にはもう、東京ではプライド・パレードも始まっていたし、探せばエンパワメントされるような本もあったはずなんですが。当時は身近にインターネットもなかったし、同じような悩みを抱えた人たちとも繋がれず、とても孤独でした。
何よりつらかったのは、親しい友達に嘘をついている、という気持ちです。年々その気持ちが重くなってきて。

──著書では、転機は大学卒業時だったと振り返っていますね。
仲の良かった女友達といった大学の卒業旅行で、カミングアウトしました。不安でいっぱいでしたが、苦しさから逃れたい一心でしたね。その子たちは高校時代から一緒に過ごした友人たちだったので、7年の付き合いだった。長年の葛藤の末の一大決心でした。
──どういう反応が返ってきましたか?
友達はみんな「早く話してくれれば良かったのに」って。すごく温かく受け入れてくれました。その後、大学院でパリに留学し、大学でLGBTのサークルに初めて参加しました。そうした諸々が重なって、自分のセクシュアリティについて、少しずつ前向きに考えられるようになりました。

自分らしく生きることが一番大切な家族を苦しませてしまうジレンマ
──ご家族へのカミングアウトは、もう少し大変だったと聞きました。
そうですね。留学中、母がパリを訪れたんです。きっと母もわかっていたんですね。母から、「女の子が好きなの?」と聞かれたんです。わたしは嘘をつきたくなかった。だから「そうだよ」といったら、母は泣き崩れてしまいました。
母も相当ショックだったんだとは思いますが、当時のわたしにとっては非常につらい言葉を投げかけられて、わたしも強い言葉で言い返してしまった。12年間の暗い時代から光が差して、自分らしく生きていけると思った矢先に、そういう出来事が起きて、つらかったです。

──その後はどういった状況になりましたか?
その後、母親とはセクシュアリティの話はタブーになってしまいましたね。社会人になってからも、しばらく実家にいた時期があったのですが、恋愛・結婚・出産については一切聞かれないし、こちらからも話さない。わたしは自分らしく生きたい。でもそのことが一番大切な家族を苦しませてしまう。そういう状況でした。

10年後、和解した母が編んでくれたレインボー・マフラー
──その後、変化はありましたか?
実は、その留学中の出来事から10年後、わたしが当事者として実名と顔を公表して活動を始める時、家族にも伝えなければいけないと考えて、改めて話したんです。
わたしは反対されたら家を出なければいけない、という覚悟で話したんですが、父親と母親は、こっちがびっくりするくらいあっさり認めてくれて、応援してくれた。父はもともと理解してくれていたのですが、その時は母も背中を押してくれて。

──どういった変化があったんでしょうか?
後で父から話を聞きました。22歳の時にわたしがパリで母にカミングアウトして、お互い傷つけあった後、母はLGBTに関する本を読んだりインターネットで調べたり、わたしのことを理解しようと、努力をしてくれていたそうなんですね。わたしからすれば、「時が止まっていた」と思っていた10年の間に、そうした変化が起きていた。
本当に嬉しくって。解き放たれた感覚でした。母は編み物が好きなんですが、わたしが自分で毛糸を買って、「レインボーはLGBTの尊厳を表す色なんだよ」って、マフラーをお願いしました。活動デビューのシンポジウムに着けて行きました。今でもとても大事なマフラーですね。

アメリカのゲイ・アクティヴィスト、ハーヴェイ・ミルクとの出会い
──そもそも、増原さんが実名で社会的発信を始めたきっかけはなんですか?
2010年、ショーン・ペン主演の『ミルク』と、ドキュメンタリー『ハーヴェイ・ミルク』に出会いました。ハーヴェイ・ミルクは1977年に米国の歴史上初めて、ゲイを公言して公職に就いたものの、翌年には暗殺されてしまった。その人生に衝撃を受けたのがきっかけです。時代も社会も違うのに、勝手に「ミルクに続かなきゃ!」って思っちゃったんです。

──増原さんからいって、ハーヴェイ・ミルクのような存在が今の日本社会に対して持つ意味はなんですか?
ミルクが遺したメッセージのひとつに「ビジビリティ(Visibility)」があります。「可視化すること」と訳されることが多いのですが、つまり「当事者の姿が目に見えること」ですね。彼は暗殺の危険性を感じつつも、当事者に勇気を与えることを選んだ。
もちろん、今の日本では、必ずしもカミングアウトが最良の方法とは限りません。だから留保つきですが、わたし自身は、「ビジビリティ」というメッセージを大事にしています。1人がカミングアウトするのを周りで10人が聞いていたら、何らかの影響を与えるはず。

カミングアウトできない環境がつくる、見えづらい問題——コンサルタントとしての経験から
──LGBT当事者にとって、企業で働くことにどのような壁がありますか?コンサルタントとしての経験でも、ご自身で働いていた時の経験でもよいので、聞かせてください。
わたしは起業して独立する前に12年間ほど会社員として働きました。レズビアンだと完全にオープンにしていたのは、最後の教育系のITベンチャー企業だけです。ばれないように嘘を重ねてストレスをためることもなく、仕事に集中できる環境でした。無理に全員がカミングアウトする必要はありませんが、やはり自分らしさを持ち込める職場環境と働きやすさは繋がっています。

──LGBTは13人に1人と言われています。啓発の現場での実感はどうでしょうか?
理解が進む一方で、全国調査でも8割ほどの人は、「身近に同性愛者はいない」と答えています。つまり、当事者と、少数の支援者以外は、身近に当事者がいるとは思ってない。職場で困っている人がいても、その存在が周りから見えていないことがまずは大きな課題です。

──LGBTに関して言えば、具体的にはどんなケースがありましたか?
よくあるのは、性的指向や性自認といったセクシュアリティについて勝手に噂されたり、ばらされたりして会社にいられなくなることです。当事者の同意なくセクシュアリティを暴露する「アウティング」ですね。嫌がらせで退職に追い込まれていることもあります。
他にもたとえば、トランスジェンダーの方で、外見は自分が望む性別に変わっているけれど、戸籍がそのままの場合、健康診断を受ければ元の性別が周囲にばれてしまう。だから正社員として働いていても、健康診断を避けるために毎年仕事を辞めている、というケースもありました。そうした問題は多くの場合、人知れず起きています。

みんなが「自分らしさ」をシェアすることで、社会は「強く」なれる
──増原さんは、LGBTに関するダイバーシティの推進は、「誰もが生きやすい社会」に繋がる、と主張しています。その理由を教えてください。
今の日本では社会的に弱い立場に置かれてしまうかもしれない個人の多様性をみんなでシェアするほうが、結果的には、各自が持っている力を発揮でき、組織は「強く」なれるんです。こうした考え方はダイバーシティ経営の分野で、ここ数年広がりを見せています。
わたしは企業などで、おもにLGBT対応に焦点を当てて講演・研修をするんですが、まずは「自分のことを語っていいんだ」という空気が重要です。研修後に、「自分もLGBT当事者です」とか「子どもが障がい者です」とか、個別に話しかけてくれることがよくあります。一人が自分らしさを開示すると、相手もさらけ出しやすくなる。そうするとみんなが安心して生きられる空間ができる。変化の兆しは感じています。

──増原さんは、一昨年から、生徒の個性を押しつぶすようないきすぎた指導や校則、いわゆる「ブラック校則」をなくそう、というプロジェクトに関わっていました。
2017年秋に大阪府立の女子高生が地毛は茶髪なのに黒髪に染めさせられて、学校側に損害賠償を訴えたと報道された時に、評論家の荻上チキさんをアドバイザーに迎え、子どもの貧困の問題に長く取り組んでいるNPO法人キッズドアの渡辺由美子さん、引きこもりや不登校の問題を扱うNPO法人ストップいじめ!ナビの須永祐慈さんとともに、プロジェクトの発起人になりました。
わたしはダイバーシティ分野で活動してきましたが、他の分野の問題と共通する課題もあるので、様々な方々と一緒になって、現場の声を聞き、社会問題化するプロセスを経験できたのは大きかったです。

みんなが感じている息苦しさを、一つひとつなくしていきたい
──とはいえ、政治活動を始める決意は、すぐにつきましたか?
実はわたしが政治活動を始めるかどうか迷っていたタイミングで、ともにLGBT関連の法改正を実現しようとしていた方が、自殺で亡くなったということを親しい人からお聞きしたんです。すごくショックで、無力感に包まれました。同時に、これはもうわたし自身が国会議員になって、マイノリティに寄り添う議員を増やすしかない、と決意した瞬間でもありました。法整備が追いつかなければ、仲間はどんどんつらい状況に追い込まれて、大切な命が失われていく。いま、変えなきゃいけない。

──これまでのダイバーシティ推進のコンサルティングでの経験は、これから増原さんが政治家として追求するビジョンにも関連していますか?
いまの社会で息苦しさを感じているのは、LGBTを含めたマイノリティだけじゃなくて、自分の生き方や価値観を否定されたり、押しつぶされたりすることへの怯えを抱えている人はたくさんいると感じます。たとえば、経済的に困っていること、障がいがあること、病気で苦しんでいること、介護を受けていることなど、社会的に弱い立場に置かれてしまうことは、誰もが当事者になるかもしれない、そういう困ったときに支え合う社会にしなければ、息苦しさはなくならない。
ダイバーシティというのは、日本の未来を考える上で、ベースとなる考え方になると思います。格差の問題も同じ。一人ひとりの権利や幸福というのをきちんと考え、再分配のあり方や、働けない人たちへのケア、働く意欲のある方々へのサポートを充実させれば、福祉政策というのは、そのまま経済政策や成長戦略になりえる。一人ひとりが尊重されて安心して働けたら、自然に社会も元気になっていくと思います。

──今後、議員として取り組みたい具体的な政策はありますか?
LGBTの差別解消法をはじめ、選択的夫婦別性や手話言語法、クオータ制や同性婚など、多様性を大切にするテーマだけでも、たくさんあります。ダイバーシティが尊重される土台という意味でも、最低賃金の引き上げ、介護士や保育士、教員の待遇改善や公正な分配、そして子どもの貧困対策など経済政策にも力を入れていきたい。原発ゼロや性暴力被害者の支援なども、早急に実現すべきだと考えます。
わたしの大きな軸のひとつは、だれもが安心して暮らせる、ダイバーシティ社会の実現です。それには、とくに教育が重要だと考えています。マイノリティに対する理解や啓発というのを超えて、一人ひとりが尊重されて、自由で認め合う社会を作っていくためには、教育や子ども、福祉への投資は欠かせません。日本の教育に対する予算の配分は先進国中、極めて低い。この問題にはぜひ取り組みたいです。

──最後に、どんな社会を実現したいですか。
どんな人でも、「社会から歓迎されている」という実感がもてる環境をつくっていきたいと強く思っています。そのためには、まずは教育の中で、かけ声だけでなく一人ひとりの個性を大切にして伸ばす風土が必要です。
社会が敷く一定のレールから外れる人たちは、凍りつくような冷たい水の中を裸足で歩いていくような過酷な環境を強いられるのが日本社会の現状です。括弧つきの「普通」から外れる人やマイノリティにはとても冷たい社会です。わたしは政治家として、その水の温度を一度でも上げていきたい。一度ずつ上げていくことで、社会を誰にとってもあたたかい居場所にしていきたいと願っています。

増原ひろこ HIROKO MASUHARA
1977年神奈川県横浜市生まれ、千葉県育ち。2000年慶応義塾大学文学部卒業後、パリ第3大学に留学、2003年慶応義塾大学大学院修士課程修了。在外公館(ジュネーブ)、会計事務所、教育系IT企業勤務などを経て、株式会社トロワ・クルールを設立。ダイバーシティ経営コンサルタントとして、NTTドコモ、みずほフィナンシャルグループなどの企業や連合中央女性集会などでダイバーシティ推進支援を展開した。2011年、LGBT当事者であることをオープンにして活動を開始。2015年、東京都渋谷区パートナーシップ証明書交付第1号(2017年末に解消)。2018年、京都造形芸術大学の学生支援アドバイザーに就任。2019年、同大の客員准教授に就任予定。著書は「同性婚のリアル」(ポプラ社)、「ダイバーシティ経営とLGBT対応」(SBクリエイティブ)など。