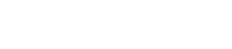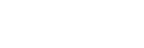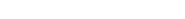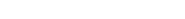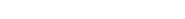兵庫 安田真理 MARI YASUDA
日本は報道の自由度に関する国際ランキングでその順位を落としてきている。「忖度」という言葉が話題となり、女性芸能人による辺野古基地問題への署名呼びかけがバッシングを受けたのも記憶に新しい。
フリーアナウンサーの安田真理は、報道関係者であっても政治的発言を控えるような風潮の中で、積極的に社会的発信を続けてきた。彼女は2011年の東日本大震災をきっかけに、それまで勤めていた地方局を辞めて上京。アナウンサーとしてメディアの現場で働きながら、大学院でジャーナリズムを学び、日本社会の現状に危機感を募らせてきた。
2018年、国会では日本の将来を左右する数々の重要法案が強行採決された。降って湧いた政治家としての活動の要請に、最初は戸惑った安田だったが、「わたしのように、もう黙っちゃいられない!と思っている人はたくさんいるはず」と今回の決断をしたという。
現在は兵庫県で精力的に活動する安田に、これまでメディアの現場で感じてきた危機感と、これからの日本が目指すべき未来について聞いた。
震災をきっかけに「モノ言うアナウンサー」へ
——自己紹介をお願いします。
安田真理です。石川県金沢市出身。地元の大学を卒業後、北陸のNHKと民放局で、テレビの番組キャスターを務めたあと、2012年からは東京でフリーアナウンサーをしていました。気づけば17年間、報道に関わり続けてきたことになります。3月から、兵庫県神戸市を拠点に政治活動を始めました。

——安田さんはアナウンサーでありながら、個人としてたびたび政治的な発信を続けてきました。きっかけは何でしたか?
2011年の東日本大震災です。報道に携わる人間として、あの震災と原発事故をメディアの内側からリアルタイムで経験して、「政治はわたしたち国民の生活と密接につながっているんだ」と強く実感したからです。
震災後、「報道の使命ってなんだ?」とずっと考えているうちに、せっかく社員にしてもらった地元放送局を辞めて、上京していました。東京ではフリーアナウンサーをしながら、ジャーナリズムをイチから学びなおそうと大学院に進学。現場では知り得なかった学問的な知見に触れることができました。

——これまで発信した中で印象に残っているトピックはありますか?
2013年に国会に提出された特定秘密保護法案です。法案に疑問を投げかける視点をブログにつづったら、取材を受けて。それが夕刊紙に大きく載ったんですよね。すると周囲から「ああいう発言はしないほうがいいよ」と言われたりもしました。
もちろん、フリーのアナウンサーという立場で政治的発信をすることにリスクがあるのはわかっていましたけど、これまで「モノ言うアナウンサー」の可能性を模索してきたつもりだったので、それなりの覚悟をもっての行動でした。
東日本大震災で感じた、政治とマスメディアへの危機感
——現在の安田さんのキャリアの転換点になっているという、東日本大震災の時のお話を聞かせてください。
あのときの地震と津波による被害を映像で見たときのショックは、いうまでもありません。加えて、東京電力福島第一原発で事故が起こりました。わたしの出身地である石川県にも原発はあります。とても他人ごととは思えなかった。
2つの原子炉で水素爆発が起きたわけですが、その爆発がいったい何を意味するのか、どんな影響を及ぼすのか、そういった重要な情報が政府からもマスメディアからもすぐには出てこなかった。政治とわたしたちの生活とが、ダイレクトにつながっていることを痛感した出来事でした。

——被災地にも足を運んだと聞きました。
2011年夏に、福島県南相馬市を訪ねました。南相馬は地震、津波の被害だけでなく原発事故の影響で屋内退避区域に指定されていました。そのためじゅうぶんな物資や情報がゆき届かず、当時の桜井市長がユーチューブで窮状を訴えて話題になりました。私が行ったとき、まだ津波の爪痕は大きく残ったままで…言葉が見つかりませんでした。
桜井市長からも話を聞きました。「とにかく全国からできるだけ多くの人に来て実態を知ってもらって、たくさんの知恵を提供してほしい」と、悲痛な面持ちで訴える姿をみて、わたしも何かしなくては、と焦る気持ちになりました。
それで、地方のテレビ局にできることはなんだろう、と考えました。全国の系列局が連携してキャンペーン報道をしてもいいし、わたし自身が取材を続けるのもいい。でもその思いは空回りするばかりで、結局、勤めていた地元テレビ局を辞めて、自分なりの被災地支援を模索することになりました。

原点は“野生児”——アナウンサーは「就活での失敗」がきっかけだった
——安田さんは子どもの頃からテレビの世界に興味があったんですか?
その逆です。なにしろうちにはテレビがなかったんですよ。父がジャン=ジャック・ルソーの『エミール』に強く影響を受けて子育てしたという、ユニークなひとなので。 わたしたち三人きょうだいは幼い頃から海や山に連れていかれて、自然に親しみながら育ちました。
森では高い木にロープを垂らしてターザンのように空中ブランコを楽しんだり、1歳から父手製のスキー板を履かされて雪山に放り込まれたり。まるで、野生児ですよね。アラレちゃんじゃないか、と言われたこともありました(笑)

——スキーでは高校から社会人まで、国体に8回も出場されているんですよね。
そう、スキーが大好きだったんですよね。でもそれだけじゃなくて、わたしは日本の義務教育システムに馴染めなかったことも、スキーに打ち込んだ理由のひとつだったように思います。
父は「なんでも好きなことを突き詰めさない」という教育方針だったので、黙って先生の話を聞くことが主体の学校教育の現場が、わたしにはものすごく窮屈で。スキーだけがわたしの友達だった、とまではいいませんが(笑)、真っ白な雪山で風を切って滑降することに大きな開放感を味わっていました。

——でも、大学では教育学部ですよね?
はい。自分が学校にうまく馴染めなかった経験から、もっと教育について考えたいと思って、大学は教育学部。でも、大学4年のとき小学校教員を目指して受けた教員採用試験が不合格になってしまって。
当時はなぜか、面接で自分のことをPRするのが、ひけらかすようでかっこ悪いと思い込んでいて。「ハイ」か「イイエ」くらいしか面接で答えなかったんです。それは落ちるでしょう、と今なら思うんですけどね(笑) 不器用なんですよ、もともと。

——そこからなぜアナウンサーに?
面接力と教員としての会話力を鍛えようと、地域のカルチャースクールにあった「話し方教室」に参加したんです。そうしたら、元テレビ局アナウンサーの講師に、NHKの番組キャスターのオーディション受験を勧められて。社会勉強になるかとダメもとで受けてみたら、なんと合格してしまったんです。その講師の先生に出会わなかったら、今のわたしはないですよね。

アナウンサーの仕事を通じて、ジャーナリズムへの関心が強まった
——実際にアナウンサーになってみて、どうでしたか?
人前に出るのが苦手だったので大変でした。一人だけアップで画面に映ると、言葉に詰まってしまって。NHK富山で4年間情報番組のキャスターを務めて、「ようやくカメラを見られるようになったね」と言われたほど(笑)

——しかし、そんな中で報道という仕事にやりがいを感じ始めたと聞きました。
テレビ局に入って最初に担当したのが、地域の情報番組でした。月曜日から金曜日まで毎日、夕方の55分間CMなしの生放送。企画から撮影、編集、出演にいたるまですべてを担当することもあって、徹夜で家に帰れないこともしばしば。とてもいい修行でした。
そんな経験があったからこそ、原稿を読むだけのアナウンサーよりもむしろ、ジャーナリストへの興味が芽生えたんだと思います。とくに好きだった取材は、何かに向かって奮闘する人たちの日常を追いかけるドキュメンタリーです。
身体のハンディキャップをもちながら世界大会に挑む女性水泳選手、数学の世界チャンピオンになった男子小学生、金沢の伝統工芸「加賀友禅」を新しい視点で広めようとする夫婦など…「現場」にいるひとたちの想いを伝えることに熱中しました。
現場で対話を重ねながら一緒にモノづくりをする、という番組作りの経験は、わたしの生きるうえでの重要な指針を形成していると思います。

「政治家ってキモい。でも真理がやるならヤバいかも」―背中を押してくれた友人の言葉
——そうした想いを抱える中で、今回政治家を目指すことになったきっかけは?
ある日突然、大学院時代にお世話になった知人から「安田さんみたいな人に政治家になってほしい、どうですか」と誘いを受けたんです。最初はすごく戸惑いました。この春からは番組キャスターの仕事、新たに大学講師として放送文化の授業を受けもつこと、日本で唯一のファクトチェック団体で活動することなどが決まっていました。メディア人のひとりとしてより活発に情報発信をしていこう、とちょうど意気込んでいたところだったんです。
それに「いまの日本の政治家は権力に魂を売っている!」くらいに思ってましたから(笑) まさか自分が政治家になろうだなんて、夢にも思わなかった。

——そうした気持ちが変わったのはなぜですか?
その知人がつないだ立憲民主党の政治家たちに会ってみたら、失礼ながら思いのほか、いい人たちだったんです。わたしはこれまで政治家を色眼鏡で見ていたのかなあ、と。そこで親友に相談してみたんです。彼女の第一声は、「政治家って国民のみなさまのため、とか言ってるけど、嘘っぽくてキモい」(笑) やっぱりそうだよねー、とうなずきかけたら、「でも真理がやるとしたらヤバいかも」って。
——どういう意味ですか?(笑)
「政治に女性が少ないのは問題でしょう。真理が入ることで、政治がちょっと動くかもしれない。普段からいろいろ政治的な発言してるし、ものすごく向いてるんじゃない?」って。
彼女はわたしが真剣に模索している「好ましい政治のあり方」をすごく理解してくれていたんですね。親友からすれば、「ジャーナリストか政治家か?」なんて、比べるほど両者に大差はなかった。わたしの新しい可能性をあっさり肯定してくれたんです。

——少しずつ現実的な選択肢になってきた感じでしょうか?
2018年も、与党の数の力による強行採決が繰り返されました。じゅうぶんな論議がされないままに、国の土台となる憲法までもが作り変えられてしまう、ということにはしたくない。わたしの問題意識からしても、立ち上がるのは今だ、と決心するにいたりました。
これまでとアプローチは違うけど、目指すものは同じ。わたしが今まで積み上げてきたことを活かして、前に進もうと思っています。

セクハラもパワハラも、他人ごとじゃない
——テレビ業界に引き続き、政治の世界もまだまだ「男社会」です。このことについては、どう考えていますか?
17年間の社会人生活のなかで、女性が仕事のうえで正当に評価されていないと感じる場面をいくつも見てきました。同じ資格をとっても男性社員と同等のポジションには就けなかったり、同一労働同一賃金ではないことも。わたし自身のいた報道現場というのも男性主体で女性は傍流ですし、パワハラやセクハラについても他人事ではなかったですね。
特定秘密保護法案の疑問をブログに投げかけたわたしの意見が夕刊紙に取り上げられたときも、見出しは「超美人アナも『秘密保護法』に反対」。女性であることを消費されただけのような気がして…生活をかけての訴えだったのに、と無力感に包まれました。
政治の世界はこれから経験しますが、女性の声がまったく足りていないようにみえます。

——フェミニズムからの影響は大きいですか?
2017年に性暴力被害を告発する#metoo運動が盛り上がりました。最近では性暴力被害だけでなく、女性やジェンダーにまつわる社会課題がクローズアップされ、顕在化してきているようです。わたしも話題になっているロクサーヌ・ゲイ著『バッド・フェミニスト』、北原みのり著『日本のフェミニズム』などを読んで理解を深めました。 でも、そうした問題はまだ十分に社会で共有されていないから、さらなる議論が必要です。
男女同数の政治(パリテ)を目指す立憲民主党のキャンペーン「パリテ・ナウ」のPV。安田も出演している
震災を乗り越えた「多様性のまち」の可能性
——今回は兵庫県での政治活動の開始です。兵庫県の歴史や可能性について聞かせてください。
兵庫県は、北は日本海から南は瀬戸内海まで、また山間部から大都市・神戸まであります。こうした地理的特徴は、多様な風土、文化、歴史、産業を根付かせてきました。1868年の神戸港開港以来、海外から新しいものや他者を受け入れてきた文化は、さまざまなところに見え隠れしています。難民や在日外国人の当事者団体やその支援団体も数多くあります。多様性のある土地柄を活かして、新しい日本のモデルを兵庫から発信していきたいですね。
また、兵庫県は1995年に起きた阪神・淡路大震災から24年の歳月をかけて復興してきました。災害に強い国づくりをするうえで、兵庫県が復旧、復興の過程で積み上げてきた知見、先駆的な取り組みは、今後も重要な役割を果たしていくはずです。

——安田さんのもともとの関心であるエネルギーについてはどうでしょう?
日本のエネルギー政策は「原発ゼロ」に背を向けはじめていますが、やはり世界的な潮流は再生可能エネルギーの推進です。兵庫からもバイオマスや水力発電、風力発電など、地域の特性を活かした再生可能エネルギーの発電システムを模索していきたいですね。
なにしろ兵庫県宝塚市には市民がつくった発電所があって、自然と共存しながらエネルギーを自給自足できるまちづくりを2012年から検討しています。ほかにもエネルギー問題に取り組む市民団体は少なくありません。地理的な多様性と市民活動の力という兵庫のポテンシャルを生かして、より現実的かつ具体的な日本のエネルギー政策を構想していきたいと思います。

——女性政策についても聞かせてください。
女性全般の雇用創出も大きなテーマです。わたしの周りでは、子育てが一段落してふたたび働こうとしても、キャリアのブランクが長くて職が見つからない人が多くなってきています。女性の人生選択の幅をもっと広げたいですね。
また、#metoo運動で顕在化した、性暴力被害者を救済する環境整備は急務だと考えています。警察機関、医療機関、カウンセリングといった支援が連携して対応できるワンストップセンターの拡充をはかりたいです。

分断から、つながり合う社会へ。不器用でも、わたしのやり方で。
——安田さんからみて今の日本はどう見えますか?
「分断」と「不寛容」が広がっているように見えます。世界的な流れでもあるかもしれませんが、日本ではとくに政治がうまく機能していない。政治が政治家だけのものになってしまって、市民とはかけ離れたものになっていると感じます。
格差の拡大、あちらこちらでみられる同調圧力も気がかりです。将来に不安を抱く人たちが増えている。そのことによって誰もが余裕を失くしてしまっているのかもしれません。
政治の仕事はその「不寛容な社会」を因数分解すること。どこに原因があるのかをみつけ、その障害を一つずつ確実に取り除いていくことだと思います。

——目指す政治家のビジョンを聞かせてください。
分断されてしまっているものを、できるだけつなぐ仕事をしていきたいです。まずやるべきは、声をあげたくてもあげられない人たちの切実な声を政治に届けること。この社会から取り残される人たちをなくしたいです。
わたしは意外とガンコで不器用なタイプ。取材相手の気持ちを大切にしたいのに、そこに編集をかけようとする上司とケンカすることもしばしばありました。政治家として、その不器用さは大切にしたい。
社会を変える方法は、必ずしも従来の政治家のやり方でなくても良いと思うんです。政治を身近に感じてもらえるよう、わたしなりのやり方で、新しい政治家像をつくっていけたら。これからも丁寧に人の話を聞いて、人と政治を、人と人を、人と制度をつなぎ合わせ、誰もが声を上げられる社会をつくっていきたいです。

安田真理 MARI YASUDA
1978年石川県金沢市生まれ。金沢大学教育学部保健体育コース卒。小学校教諭免許、中・高校保健体育教諭免許を持つ。大学卒業後、NHK富山放送局で番組制作とアナウンサー、石川テレビでアナウンサーを務める。
2012年からフリーアナウンサーとしてテレビ、ラジオ、ナレーションなど様々な場面で活動。近年は金融経済番組を担当。2013年には舞台『バイオハザードカフェで朝食を』に出演。2015年に日本政策学校を修了。法政大学大学院社会学研究科社会学専攻で研究し、修士論文「原発震災と『三月ジャーナリズム』の課題と可能性」を提出して2018年に修了。
2019年、大正大学非常勤講師に就任予定。特技は1歳から始めたスキー。国民体育大会冬季大会に8回の出場経験がある。趣味はダジャレ、映画。